- TOP
- COFFEE BREAK
- コーヒー焙煎士、パリの流儀 Vol.1
- コーヒー焙煎士、パリの流儀 V…
COFFEE BREAK
文化-Culture-
コーヒー焙煎士、パリの流儀 Vol.1
焙煎は、味のヴィジョンを実現すること。
「もともとはコーヒーが嫌いだった」。パリの名シェフがコーヒーを託し、業界での評価も高い焙煎士からは、意外な言葉が返ってきた。美食の都で活躍する個性豊かな仕事人たちの流儀に迫る新連載。

Hippolyte Courty
イポリート・クルティ
1975年パリ生まれ。歴史研究者、食・ワインのライターを経て、コーヒー焙煎士へ転身。毎日焙煎を行う、Probatの最新型(12kg)とともに。
アラン・デュカスやピエール・エルメとコラボし、独特の「フランスらしい美食的なコーヒー」を焙煎すると評判のイポリート・クルティさん。2008年にコーヒー業界に入るまではなんと、コーヒーが嫌いだったと笑う。
「苦くて焦げっぽいだけの飲み物だと思っていたんです。でも、ある機会に『カフェオテック』(パリ市内にあるシングルオリジンコーヒーの名店)でグアテマラのプルカルを飲み、あっ、と目覚めた。舌に快適な振動が残る、美食の喜びをあたえてくれるコーヒーがあるんだ、と」
ところが当時のパリでは美食的、つまり「均整と調和のとれた味の美しさで感動させ、幸福な気持ちにさせる」という観点で焙煎を行う人は見当たらない。飲食業界の仲間と語るうち、それならば自分が、と一歩を踏み出した。焙煎技術を学び、産地に足を運び、試飲を重ね、自分が求めるコーヒーの「風味のパレット」を広げていった。
「コーヒーが嫌いだったからこそ、定型に縛られず、自由な感性で風味を追求できた部分もあると思います」
このコーヒー豆を、どの高みまで持っていけるか。
そんな彼にとってコーヒーとはまず、「繋ぐもの」。栽培・加工・焙煎・抽出と、関わる人が順番に豆を抱えて次にパスし、飲む人まで繋げていく、ラグビーと似た世界だと考えている。
それを踏まえて、「その豆がどの高みまでいけるのか、ヴィジョンを持って焙煎すること」が、彼の流儀だ。
「生豆の香気成分は30種ほどですが、それが発酵で300種に、焙煎を経て800種まで拡大します。生豆を前に、これをどこまでいいものに広げていけるのか、を自問するんです」
生豆が届くと、豆ごとの情報(形、精選のタイプ、湿度、濃度......)をすべてデータ化する。そのデータベースと、納品の際に生産者と交わす会話が焙煎のスタート地点。そこから仕上がりの味を定めるのは、直感が頼りだ。
焙煎が成功した時の風味の表現は当然、豆ごとに異なるが、彼自身の状態は共通していて、「自分が空になって、瞑想しているような気分になっている」という。「そういう時は、私の思いや熱意を豆に込められたということです。豆は、焙煎士の心をのせて運ぶもの。〝美味しいコーヒー〟というのはそれを飲む人に伝えて、柔らかく、ポジティブで、豊かな気持ちにしてくれるものだと思っています」

必需品は試飲スプーン
「焙煎士になくてはならない道具」との問いに答え、カッピング時の試飲スプーンを選んだ。店のロゴ入りの特注品だが、製品自体はスタンダード。レユニオン島のブルボンポワントゥと。

オリジナルの賞味カップ
愛するのは、エスプレッソの香りの豊かさとクレマ。その賞味にふさわしいカップを開発し、昨年商品化した。試作は400回に及び、型の採用前には内部構造をレントゲンで調べたことも。

生産者との直取引を重視
12の生産者の豆を20~30種扱い、その8割は直取引。ほぼ同じ比率を循環型農業の豆が占める。焙煎する豆は品種・畑・発酵に至るまですべて単一で揃え、ピュアな味の表現を追求する。
 L’Arbre À Café
L’Arbre À Caféラルブル・ア・カフェ
焙煎を行うアトリエ(右写真、142 rue du Maine, 75014 Paris)では、一般向け、プロ向けの各種コーヒークラスを開催。豆はブティック(10 rue du Nil, 75002 Paris)で販売。
www.larbreacafe.com

 健康
健康 美容
美容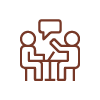 インタビュー
インタビュー 文化
文化 世界のコーヒー
世界のコーヒー 基礎知識
基礎知識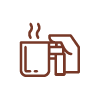 楽しみ方
楽しみ方